涼香が入院してしまったことで、田中は新たなタレントを必要としていた。視聴率を稼ぐためには新鮮な顔が不可欠だった。
だが、面倒な手間は嫌いな田中は、子分に丸投げし、オーディションの準備を一任していた。
今回は地上波ではなく、配信サイト向けの企画。素人の応募者にはギャラは一切出さず、配信からの収益は全て田中の懐に入る姑息な仕組みだった。
子分はスタジオの段取りを整え、今日はいよいよその第一歩が始まる日だった。
東京某所の某スタジオに、期待と緊張が入り混じった空気が漂う。スポットライトがスタジオを照らし始めた。

ドアが開き、一人の女が姿を現した。ピンクのビキニに包まれた身体、黒髪のロングヘアーが輝くように揺れる。彼女の名前は紗良。緊張した足取りで、スタジオの中央に立った。
子分がマイクを手に、事務的な口調で尋ねた。
「名前は?」
「紗良です」と彼女はハキハキと答えた。
「君の夢は?」子分が続けて尋ねる。
「タレントになることです!」紗良の目はキラキラと輝き、夢への情熱が伝わってきた。
子分は一瞬黙り、目を細めてから言った。「芸能界は厳しいけど大丈夫?」
「はい!今日は頑張って、ビキニを着てきました」と紗良は胸を張り、ピンクの水着をアピールするように軽くポーズを取った。

数人のスタッフが小さく笑い、スタジオに軽いざわめきが広がった。
「ではカメラに向かってポーズして」と子分が指示。
紗良はすぐに笑顔で両手を広げ、モデル風に体をひねった。

子分が手を叩き、「いいねいいね!」と褒めると、彼女の顔にほっとした表情が浮かんだ。
「では外のベランダでもカメラテストしようか」と子分が提案。
紗良は「はい」と元気よく頷き、スタジオの外へ移動した。

朝の陽光が彼女の肌を照らし、黒髪が風に揺れる姿は絵になる。
子分がカメラを構え、「いい笑顔だね」と褒めながら、「胸に手を当てて」と意外な指示を出した。
紗良は一瞬戸惑ったが、「芸能界はこれくらい…」と自分に言い聞かせ、恥ずかしそうに両手を胸元に置いた。

顔が赤らみ、スタッフから「いいよいいよ!」という声が飛び、彼女はますます縮こまった。

「ではスタジオに戻ろう」と子分が呼び、テストは室内に戻った。
だが、次の指示がさらにハードル高く感じられた。
「次はブラを引っ張ってズラして」と子分が平然と言い放つ。
紗良の目が丸くなり、
「え!?」と声を上げた。
子分はにこやかに、
「芸能界に入るためだ。頑張って」と説得する。
紗良の心は大混乱だった。人前で水着を着るのはこれが初めてで、すでに緊張と恥ずかしさでいっぱいだった。それなのに、「ここまでするなんて…」と頭の中で繰り返し、身体が熱くなるのを感じた。
だが、夢への一歩と信じて、震える手でビキニのトップに触れた。
ズラしすぎないよう慎重に、少しだけ引っ張り、わずかにずらす。
心臓がドキドキと鳴り、観客の視線が刺さるようで、
「恥ずかしい…」と内面で叫んだ。
それでも、「こうですか…」と呟き、

「これでいいですか…」と小さな声で確認した。
顔は真っ赤になり、足元がふらつくほどだった。
その時、バックステージから田中が現れ、腕を組んでコメントした。
「うーん。物足りないなー。それじゃテストにならないよ。おいスタッフ!手伝ってあげて」
冷ややかな声に、紗良の顔から血の気が引いた。
「ええ!?」と叫び、慌てて手を離すが、すでにカメラは彼女の反応を捉えていた。
田中はニヤリと笑い、子分に耳打ちする。「この子、素材としては悪くない。もっと恥ずかしがらせてみてくれ。涼香の穴を埋めるには、これくらいじゃ足りないからな」
スタジオの空気は一変し、紗良の心臓は高鳴った!
————————————————
一方その頃…
涼香の意識は深い闇の中を漂っていた。
麻酔の眠りに沈んだ後、身体が重く、頭がぼんやりとする。すべてが混ざり合い、「死にたい…」と呟いたあの瞬間がフラッシュバックする。
やがて、瞼が重く持ち上がり、視界がぼんやりと開いた。
マットレスの感触が背中に伝わり、目の前には暗い色の天井が広がっていた。
ベッドの上に横たわる自分の身体に気づき、慌てて上半身を起こす。
だが、腰の痛みは消え、代わりに奇妙な軽さを感じた。
「ここは…どこ?」と呟き、辺りを見回す。
薄暗い部屋、小さな窓がはまった壁、消毒液の匂いが漂う空気。病院のようだが、どこか異様な雰囲気が漂っていた。

その時、視線の端に人影が映った。
近くに男が立っている。白衣を着た体型に、独特な表情の顔。
涼香の心臓が跳ね上がり、反射的に叫んだ。

「いやああ!あんた誰?ゾンビ!?」
声が部屋に響き、恐怖で身体が震える。
男がゆっくりと振り返り、冷ややかな目で彼女を見据える。
「俺はゾンビじゃない。失礼な奴だな」と低い声が返ってきた。
男は鼻を鳴らし、片手をポケットに突っ込む。
涼香は息を呑み、警戒しながら尋ねた。
「…看護師?」
男は一瞬黙り、口元に薄い笑みを浮かべて答えた。
「看護師じゃない。監護士だ。この監禁病棟を護っている」
その言葉に、涼香の胸が締め付けられる。
監禁病棟――警察に麻酔銃で撃たれ、運ばれた先がここだと気づいた瞬間、恐怖が全身を支配した。
監護士はさらに続けた。
「お前は精神病と暴行罪でここに移送された。しばらくは外に出られない」
冷たく淡々とした口調に、涼香の頭が混乱する。
「そんな…!何!?精神病!?暴行罪!?」と叫び、ベッドから飛び起きようとしたが、身体が思うように動かない。
手首に冷たい金属の感触――手錠がかけられていることに気づき、絶望が広がった。
「嘘…こんなの…」と呟き、涙がこぼれそうになる。
「スマホは!?」とすがるように尋ねた。
ファンの声、応援のコメント――それが彼女を支える最後の希望だった。
だが、監護士は無表情で首を振った。
「お前の精神が安定したと判断されるまでは無理だ。今は諦めろ」
その言葉が、涼香の心に重く突き刺さった。
「そんな…スマホが…」と声が途切れ、言葉にならない感情が喉を詰まらせる。
スマホがないという現実は、彼女を孤立させ、絶望の淵に突き落とした。
部屋を見回すと、小さな窓から差し込む薄い光が、監禁の現実を強調していた。涼香の心は崩れそうだった。
監護士が一歩近づき、彼女の肩に手を置く。
「落ち着け。暴れればもっと辛くなるだけだ」と言い、冷たい視線を向ける。
その手は、かつての昭和病棟での不適切な触診を思い出させ、涼香の身体が硬直した。
「触らないで…!」と叫び、反射的に手を振り払おうとするが、手錠に阻まれ、力なくベッドに沈む。
頭の中では、「だまされているぞ」というファンの声がこだまする。警察の「上級国民に対する正当防衛など、無い」という言葉が蘇り、社会の不条理が彼女を圧倒する。

「なぜ…私がこんな目に…」と呟き、目を閉じる。だが、その暗闇の中で、希望は見えず、ただ孤独が広がるばかりだった。涙が頬を伝い、嗚咽が漏れる。ベッドの上で膝を抱え、涼香は静かに泣き続けた。監禁病棟の冷たい壁に囲まれ、彼女は絶望の底で一人取り残されていた。

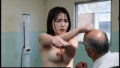
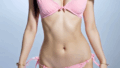
コメント